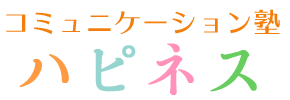子どもたちは、話したがっている ⑰ 事例④ 『先生、私も見て!』

(8月納涼歌舞伎を観てきました)
いまどきの子どもたちの気持ちや考えていることについて、考えています。
スクールカウンセラーとして勤務していると、保護者や先生から「子どもたちが話さない」という相談をよく受けます。
そんな『話さない(と思われている)子どもたち』ですが、実は『自分の気持ちを分かって欲しい』と絶えず思っています。
そのため、子どもたちは『自分の気持ちを分かってくれそうな大人』を絶えず求めています。
そんな『気持ちを分かってくれそうな大人』になるための第一歩は、子どもの話をきちんと聴くこと(良い聴き手になる)ではないかと考えます。
しかし、実際に子どもたちに寄り添って話を聴いていると、いろいろな悩みが生じてきます。
その1 「話をきちんと聴きたいけど、同じ話がエンドレスに続いて正直疲れる」(以下の詳細については、以前のブログをご覧ください)
知っておきたい知識・スキル①
『本当の困りごとは、水戸黄門の印籠と同じく、終わり10分前に出てくる』
知っておきたい知識・スキル②
『【枠】をつくってあげる方が、話しやすいときもある』
その2 「話を聴いても、気の利いたアドバイスするって難しい‥」
知っておきたい知識・スキル①
『「気持ちをわかる」とは、「分かる」であって、「判る」「解る」ではない』
その3 「話し上手っているけど、聴き上手もいるの?」
知っておきたい知識・スキル①
『「聴き上手」のためには、波長合わせが大切』
知っておきたい知識・スキル②-1(この詳細は、前回のブログを参照ください)
『話を聴けないのは、相手を信じていないから?』
知っておきたい知識・スキル②-2
『話を聴けないのは、自分自身にOKと言えないから?』
第2部 具体的な事例をもとに考えてみます。
事例1 「うーん、訊き方下手!『大丈夫か?』では、誰も答えないよ」
知っておきたい知識・スキル①
『気になる話題を細かく具体的に尋ねることで、子どもが話す事柄が明確になり、話しやすくなる』
事例2 「先生、あなたの進路ではなく私の進路です」
知っておきたい知識・スキル①
『相手の相談にのるときに大切なことは、DoingではなくBeing』
知っておきたい知識・スキル②
『こころの動きは、言葉の動きよりも遅い』
事例3 「先生の偏見で、私を見ないでください」
知っておきたい知識・スキル①
『自分の色眼鏡・物差しをはずして、子どもと向き合おう』
(ここからが、今回の内容です)
事例4 「先生、私も見て!」
前回取り上げた事例(以下)から、もう一つ考えてみたいことがあります。
中学2年生のAさんが、野外学習を前にしてこのごろつまらなさそうにしています。相談室で話をきいてみると、Aさんが言うには「来週野外学習の班決めをするのですが、うちのクラスには学校を休んでいるBさんがいます。小学校の頃から、そういう時にはいつもBさんと同じ班になっていました。先生から頼まれた時もあるし、それほど嫌でもないので、引き受けていました。でも、たまには私も仲良しと一緒になりたいと思って‥この前、先生にそのことを話してみたら、『そうか、今まで悪かったね。考えてみるわ』と言ってくれたのですが、今朝『やっぱり同じ班になってほしい』と言われてしまって‥どんどん話が進んでしまって‥構わないけど、何だか気分はブルーです」とのことでした。
前回は「先生たちは、自分のもっているイメージで、子どもを見ないで」とお話しましだが、今回はさらに根本的なことを考えてみます。
一般的に、学級担任は各学期末(2学期制の場合は、それぞれの期の終わり)に通知表、年度末に指導要録に、担任をしている学級の子どもたちの様子を『所見』という形で記述します。
この記述については、子どもから保護者からさらに教員自身からも、さまざまな意見がありますが、そのことについてはまた別の機会に考えるとして‥
先生方に問います。
「所見」を書くときに、悩むことはありませんか?
ある先生から「こどもについての所見をたくさん書ける生徒もいれば、なかなか書けない生徒もいて困ります」という相談を受けたことがあります。
いがですか?
まさしく、先生あるあるではないでしょうか?
では、どのような生徒の所見が書きやすくて、その反面どのような生徒が書きにくいですか?
「先生、先生」とことあるごとに近くに来て、話しかけてくれる子は、記述することがいろいろあるのではないですか?
それに対して、集まってくる子どもたちの後ろにいる子、勉強も運動もそれほど得意ではないけれども、かと言って特に苦手というわけでもない、言わば「目立たない普通の子」については、「あの子について何を書こうか」と今まで悩ん
できたのではないでしょうか?
すでに、答えは出ているかと思います。
つまりは、教師等周囲の大人が、「よく見ている子ども」と「よく見ていない子ども」がいるからと考えます。
(さらには、もしかして相性もあるかもしれませんね)
そして、その責任は誰にあるのでしょうか。
「目立たない子ども」ですか?「先生、先生と言って近くに来ない子ども」ですか?
いいえ、違いますよね。
すべての子どもを見てこなかった(見ようとしなかった)私たちに、責任があると考えます。
そう思うと、「所見」が書けなかったことは、「その子を見ていなかった」と、自分を振り返る良い機会を得ることができたととらえることができますね。
「所見がかけた」「所見が書けなかった」を自分自身を振り返るチェックポイントとして、すべての子どもと向かい合っていきましょう。
知っておきたい知識・スキル①
『目立つ子、目立たない子すべて、私のクラスの子』
こうした身近な問題をもとに、参加者全員で話し合ったり、ロールプレイでスキルの練習をしたりする会【コミュニケーションカフェ】を開いています。
リアルでもOnlineでも開催しています。
詳しくは、このHPのトピックスをご覧ください。