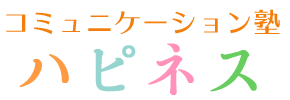子どもたちは、話したがっている ⑮ 事例③ 『心』の速さは『言葉』よりもずっと遅い

(県立大学 巣の近くのツバメ)
いまどきの子どもたちの気持ちや考えていることについて、考えています。(詳細については以前のブログ参照)
スクールカウンセラーとして勤務していると、保護者や先生から「子どもたちが話さない」という相談をよく受けます。
そんな『話さない(と思われている)子どもたち』ですが、実は『自分の気持ちを分かって欲しい』と絶えず思っています。
そのため、子どもたちは『自分の気持ちを分かってくれそうな大人』を絶えず求めています。
では、我々大人はそんな彼等に対してどのように対していけばいいのでしょうか。
それは、ありふれた表現になってしまいますが、根気よくきちんと接することと考えます。
では、根気よくきちんと接するためには、どうすればよいのでしょうか?
その第一歩は、子どもの話をきちんと聴くこと(良い聴き手になる)ではないかと考えます。
しかし、実際に子どもたちに寄り添って話を聴いていると、(経験された方は分かると思いますが)いろいろ大変なこともありま
す。
(以下の詳細は、以前のブログを参照ください)
その1 「話をきちんと聴きたいけど、同じ話がエンドレスに続いて正直疲れる」
知っておきたい知識・スキル①
『本当の困りごとは、水戸黄門の印籠と同じく、終わり10分前に出てくる』
知っておきたい知識・スキル②
『【枠】をつくってあげる方が、話しやすいときもある』
その2 「話を聴いても、気の利いたアドバイスするって難しい‥」
知っておきたい知識・スキル①
『「気持ちをわかる」とは、「分かる」であって、「判る」「解る」ではない』
その3 「話し上手っているけど、聴き上手もいるの?」
知っておきたい知識・スキル①
『「聴き上手」のためには、波長合わせが大切』
知っておきたい知識・スキル②-1(この詳細は、前回のブログを参照ください)
『話を聴けないのは、相手を信じていないから?』
知っておきたい知識・スキル②-2
『話を聴けないのは、自分自身にOKと言えないから?』
第2部 具体的な事例をもとに考えてみます。
事例1 「うーん、訊き方下手!『大丈夫か?』では、誰も答えないよ」
知っておきたい知識・スキル①
『気になる話題を細かく具体的に尋ねることで、子どもが話す事柄が明確になり、話しやすくなる』
事例2 「先生、あなたの進路ではなく私の進路です」
前回、以下の事例を基に考えてみました。
「彼女は、本人曰く『なんちゃって進学校』(有名大学の合格実績を上げることに学校全体が熱心だけど、実はそんなに大したことはない)卒業ですが、2年生の3学期あたりから、先生たちに「どこが希望?」とよく尋ねられたそうです。「先生たちが、心配してくれるのは有難かったけど、もうちょっとほかっといて」という気持ちだったそうです。しかし、サークルなどでお世話になった先生がとても親身になってくれるので、「語学なんて勉強したいなぁ」と言った途端に、「家から通える方がいいのか」「私大か公立か」「語学を勉強して、どんなキャリアを目指すのか」等と、立て続けに質問されて、まだ何も具体的に考えていなかった彼女は、とても面喰ったそうです。
「今では、先生が自分のことを心配してくれたと有難く思うこともありますが、やはりそのペースに乗せられて、私を残して大学が決まってしまったという気持はあります。この大学、好きですけど‥」とのことでした。
そして、その際に『ガイダンス』と『カウンセリング』の違いについても、以下のように説明しました。
① 物事の説明をする ガイダンス
② 相手の気持ちに寄り添う カウンセリング
そして、前回考えたスキルは
知っておきたい知識・スキル①
『相手の相談にのるときに大切なことは、DoingではなくBeing』
(ここからが、今回の内容です)
この事例から、もう一つ学びたいことがあります。
それは、『心』と『言葉』の速さの違いです。
前回の事例で、大学生は「先生たちが自分のことを心配してくれている」ということは、納得しています。
また、実際『語学』というものに興味関心があり、どうやら来春の卒業後には『語学』を生かした就職先に進むようです。
そしてまた、彼女は周囲とのコミュニケーションにも長けており、周囲とも屈託なく関係性が築けるタイプです。
ですから、「公立か市立か」や「家から通うか部屋を借りるか」という話し合いもすべて理解できています。
そこで、先生と交わされている『言葉』の意味は十分分かっていて、理解もできています。
では、何が問題なのでしょうか。
それは、彼女の『こころ』が先生と彼女の会話のテンポについていけていないからと考えます。
みなさんも、そうしたことって経験されていませんか?
例えば、「明日のプレゼンに向けて、チームでリハーサルをしている。自分が中心としてひっぱってきたが、母親が昨日入院した。検査入院と言うものの、やはり心配。若手の質問に応えているものの、周囲から見ると何だか上の空状態」
としたならば、あなたの『こころ』はどこにあるのでしょうか。
質問に対して、口は動いています。
言葉は、さして的外れではありません。
でも、あなたの『こころ』には、気持ちは入っていません。
しかし、もしもお母さんが入院して1,2週間も経ち、その状況に慣れていれば、あなたの『こころ』も違うと思うのです。
今は、状況の変化のスビートに『こころ』が付いて行っていないということではないでしょうか。
このように、『こころ』の動きはとてもゆっくりしているのです。
大学生のケースで、先生が矢継ぎ早に質問しないで、一つ質問して「○○日までに考えてきて」だったら、次回の話し合いで「私は○○と思いましたが、それって難しいですか?」と、彼女から質問して進路相談をリードしていけたのでは
ないかと考えます。
こうした状況を考えて、前回は「相手の気持ちに寄り添う」ことの大切さにさいて、お話しました。
今回は、さらに加えて『こころの動きは言葉よりもゆったりしている』ということを、考えました。
知っておきたい知識・スキル②
『こころの動きは、言葉の動きよりも遅い』
こうした身近な問題をもとに、参加者全員で話し合ったり、ロールプレイでスキルの練習をしたりする会【コミュニケーションカフ
ェ】を開いています。
リアルでもOnlineでも開催しています。
詳しくは、このHPのトピックスをご覧ください。