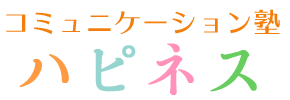子どもたちは、話したがっている ⑧提案『好きなように話す‥って、実はかなり苦しい』

いまどきの子どもたちの気持ちや考えていることについて、考えています。(詳細については以前のブログ参照)
スクールカウンセラーとして勤務していると、保護者や先生から「子どもたちが話さない」という相談をよく受けます。
そんな『話さない(と思われている)子どもたち』ですが、実は『自分の気持ちを分かって欲しい』と絶えず思っています。
そのため、子どもたちは『自分の気持ちを分かってくれそうな大人』を絶えず求めています。
では、我々大人はそんな彼等に対してどのように対していけばいいのでしょうか。
それは、ありふれた表現になってしまいますが、根気よくきちんと接することと考えます。
では、根気よくきちんと接するためには、どうすればよいのでしょうか?
その第一歩は、子どもの話をきちんと聴くこと(良い聴き手になる)ではないかと考えます。
しかし、実際に子どもたちに寄り添って話を聴いていると、(経験された方は分かると思いますが)いろいろ大変なこともありま
す。
その1 「話をきちんと聴きたいけど、同じ話がエンドレスに続いて正直疲れる」
ここで、まず知っておきたいことは『困った子は困っている子』ということです。
その上で、ではどうするとよいでしょうか?
知っておきたい知識・スキル①
『本当の困りごとは、水戸黄門の印籠と同じく、終わり10分前に出てくる』
私が教員として、またスクールカウンセラーとして子どもや大人と接していたときに、よく感じたこととして『大切な話題は(相談
者が本当に話したいこと)は、相談時間の40分過ぎに現れる』という傾向があります。(水戸黄門の印籠が出る頃といった感じでし
ょうか)
例えば、「子どもが不登校で困っている」というお母さんの相談は、最後の10分のところで「同居している義父義母から『我が家の
家系には学校へ行かない子なんていない。あなたの育て方が悪かったのでは?』と言われて、辛い」という話でした。
皆さんも、そのような体験をされたこと、ありませんか?
以前にもお話したかと思いますが、『本当に困っている人は、自分が何で困っているか』を分かっていないものです。
ですから、カウンセラーとの対話を通して、『自分が何で悩んでいるか』を、自分で見つけ出していくのです。
そして、ここで初めて『自分との対話』が始まっていくのです。
(私たちカウンセラーは、言わばそのためのお手伝いをしているといったところでしょう)
そう考えると、『本当に困っていることが出てくるまでの時間』は、決してむだなものではないのです。
この時間は、意味あるものだということが分かっていただけたでしょうか。
知っておきたい知識・スキル②
『【枠】をつくってあげる方が、話しやすいときもある』
スキル①で『本当に困っていることが出てくるまでの時間は、決してむだなものではない』ということを、ご理解いただけたと思い
ます。
しかし、それまでに時間はかなりかかっています。
子どもたちも、大人たちもお互いに時間が無限にあるわけではありません。
それに、長い時間話すということに、大人もそうかもしれませんが、多くの子どもは慣れていません。
そうすると、どうなるでしょう。
子どもたちは飽きてきます。
集中力が切れてきます。
そういう状態になっても、『話し合う』を続けることからは、建設的な有意義な結果は望めないと思います。
そこで、『話し合う』ときに、【枠】を設定するのは大切なことと考えています。
(子どもどうしの人間関係形成を目指して、『アドじゃん』というアクティビティをよく活用しています。内容は後述しますが、子どもたちはノリノリになります。しかし、いつも『アドじゃん』開始2,3分のところで終了としています。子どもたちは「えっー、もっとやりたい」と口々に言いますが‥。それは、何か興味深い活動に取り組むと、子どもたちの集中力はすごい勢いで右肩上がりで上昇しますが、あるところでバタッと急降下するからです。そこで、子どもたちの集中力の持続性を考慮して、「まだやりたい」の声が上がる内に、終了しています。『アクティビティ』ばかりでなく、『話し合う』にも同様の傾向があると考えています。)
そして、おそらくこの傾向は、『アクティビティ』よりも『話し合う』ことで大きいのではないかと考えています。
そうすると、ここで話を聴いている側としては、矛盾というか葛藤が生じますよね。
つまり『話の核心にせっかく触れたところなのに、相手は集中力が切れかかっている。ここで終了とするのはもったいない気がす
る。しかし、気持ちがのらなくなっているときに話を継続して意味があるか』ということです。
難しいですね。
皆さんならば、どう思われますか?
私ならば原則的に、今回はここで終了とします。(自死願望等、生命に関係するケースは異なります)
それは、一見相手に対して「冷たい」ように思われるかもしれませんが、むしろ相手に対して支援の手を差し伸べていることと考え
ています。
今までにたくさんの子どもたちゃ保護者、先生と話し合ってきました。
中には、強引に【時間制限】を乗り越えて、お話が続いた場合もありましたが、そうした時には「話が堂々巡りのエンドレスとな
り、私もですが相手もとても疲れた」と体験したことが記憶に残っています。
『本当に困っている』ことが、たった1回の『話し合う』ことで、解決するはずもないのです。
そこで、相手の子どもに「今日は、どんなことで困っているかがよく分かりました。残念ながら、私は魔法の杖を持っていないので、ここで魔法で解決することはできません。でも、あなたの『困りごとの種子』が分かったということは、一歩前進だよね。次回までに、私もどうすればよいかほを考えるからあなたも考えてきて。そして、次回はお互いの考えで話し合いましょう」と、説明してして、この時は終了とします。
いかがでしょうか。
時間の【枠】をつくることは、困って相談にきた子どもや大人に対して、一見冷たそう・薄情に見えるかもしれませんが、相手はも
ちろん、こちらも守るという大切なことだと思います。
【枠】を設定しましょう。
そして、それを意識して話し合っていきたいと考えます。
次回も子どもの話をきちんと聴くこと(良い聴き手になる)について、考えていきましょう。
こうした身近な問題をもとに、参加者全員で話し合ったり、ロールプレイでスキルの練習をしたりする会【コミュニケーションカフ
ェ】を開いています。
リアルでもOnlineでも開催しています。
詳しくは、このHPのトピックスをご覧ください。