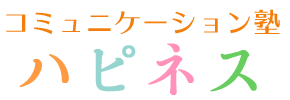子どもたちは、話したがっている ⑦提案『本当の悩みは相談終了10分前に出てくる』

いまどきの子どもたちの気持ちや考えていることについて、以下のように考えてきました。
(詳細については、以前のブログをご覧ください)
↓
保護者や先生から、「子どもたちが話さない」という相談をよく受けます。
その理由として、以下の3点を考えました。
①「言いたいことはあるけれども、どのように話していいかが分からない」
②「ここで何か言ったら、それ以上にいろいろ聞かれて面倒くさくなるのではないか」、
③「どうせ話しても、何ともならない」
↓
しかし、そうした子どもたちですが、実は『自分の気持ちを分かって欲しい』と絶えず思っています。
そして、子どもたちは『自分の気持ちを分かってくれそうな大人』を絶えず求めています。
↓
そんな子どもたちに対して、我々大人はどのように対していけばいいのでしょうか。
それは、ありふれた表現になってしまいますが、根気よくきちんと接することと考えます。
↓
では、根気よくきちんと接するためには、どうすればよいのでしょうか?
その第一歩は、子どもの話をきちんと聴くこと(良い聴き手になる)と思います。
その1 「話をきちんと聴きたいけど、同じ話がエンドレスで続いて正直疲れる」
ここで、知っておきたいことは『困った子は困っている子』ということです。
そして、これは子どもに限りません。
『困った人は困っている人であり、困った先生は困っている先生』なのです。
では、どうするとよいでしょうか?
↓
取り組み その1 『本当の困りごとは、水戸黄門の印籠と同じく終わり10分前に出てくる』
私が教員として、またスクールカウンセラーとして子どもや大人と接していたときに、よく感じたこととして『大切な話題は(相談
者が本当に話したいこと)は、相談時間の40分過ぎに現れる』という傾向があります。(水戸黄門の印籠が出る頃といった感じでし
ょうか)
「中間テストの結果が良くなくて‥」と相談室に来た中学生の話はころころと変わり、40分過ぎに「あのさ、お母さんとお父さんが
よくケンカしているんだよね」という話題が出てきました。続けて話を聴くと、リビングから漏れ聞こえた両親の会話には『離婚』
という言葉もあったそうで、生徒は「どんな話か知りたいけど、知るのも怖くて‥」といつもの「うるさい」と叱られている元気さ
とはかけ離れた様子です。そんな子でも、なかなか打ち明けられずに、「中間テスト」の話でお茶を濁していたというわけです。
これは子どもに限ったことではありません。
「子どもが不登校で困っている」というお母さんの相談は、最後の10分のところで「同居している義父義母から『我が家の家系には
学校へ行かない子なんていない。あなたの育て方が悪かったのでは?』と言われて、辛い」という話でした。
なるほどねと妙に納得しました。
どうでしょう。
皆さんも、そのような体験をされたこと、ありませんか?
以前にもお話したかと思いますが、『本当に困っている人は、自分が何で困っているか』を分かっていないものです。
ですから、カウンセラーとの対話を通して、『自分が何で悩んでいるか』を、自分で見つけ出したいくのです。
そして、ここで初めて『自分との対話』が始まっていくのです。
(私たちカウンセラーは、言わばそのためのお手伝いをしているといったところでしょう)
そう考えると、『本当に困っていることが出てくるまでの時間』は、決してむだなものではないのです。
この時間は、意味あるものだということが分かっていただけたでしょうか。
でも、そう考えると『本当の悩みが出てきたら、そこからの相談はどんどん長くなって‥言わばエンドレス?』と思われる方もいら
っしゃるのではないでしょうか?
いいえ、そんなことはありません。
それについては、次回お話します。
こうした身近な問題をもとに、参加者全員で話し合ったり、ロールプレイでスキルの練習をしたりする会【コミュニケーションカフ
ェ】を開いています。
リアルでもOnlineでも開催しています。
詳しくは、このHPのトピックスをご覧ください。