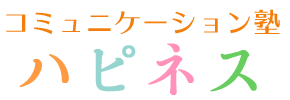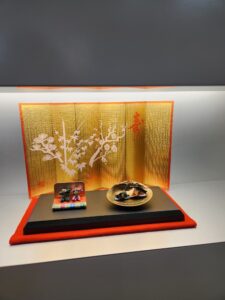子どもたちは、話したがっている ⑤『どうせ話しても、何ともならない』への回答

いまどきの子どもたちの気持ちや考えていることについて、目下考えています。
保護者や先生から、「子どもたちが話さない」という相談を受けて思うことは、保護者も先生も「子どもの(人の)話を訊くこと
が、上手ではないのでは?」ということです
まず第一に質問が具体的ではないと、考えます。
例えば、「大丈夫?」と尋ねられたら、まず大半の子どもたちは「大丈夫」と答えることでしょう。
(私たちもそうではないでしょうか‥)
では、なぜでしょうか。
その理由として、以下の3点を考えました。
①「言いたいことはあるけれども、どのように話していいかが分からない」
②「ここで何か言ったら、それ以上にいろいろ聞かれて面倒くさくなるのではないか」、
③「どうせ話しても、何ともならない」
今までに、①「言いたいことはあるけれども、どのように話していいかが分からない」、②「ここで何か言ったら、それ以上にいろ
いろ聞かれて面倒くさくなるのではないか」について考えてきました。(内容については、以前のブログをご覧ください)
そこで、今回は③「どうせ話しても、何ともならない」について考えます。
さて、「どうせ話しても、何ともならない」と、子どもたちはどうして思うのでしょうか。
大前提として、子どもたちは身体と同じように、心も成長期にあります。
今、小学校のスクールカウンセラーとして働いていますが(写真は卒業式の様子です)、彼等と接していると、同じ『小学生』と一
口ではくくられない、大きな違いを感じます。
1年生の子の「僕は何も悪いことをしていないのに、先生が僕だけを叱った」という涙ながらの訴えを聴いた1時間後に、6年生の
子の「この頃、仲良しだった子と話が合わなくなってきました。どうすればいいですか?」との相談を受けると、隔世の感がありま
す。
また、以前中学校教師として働いていたときには、1年生の「家で、勉強のことばかり言われて嫌になる」といった話の後で、3年
生の「受験校を決めたけど、本当にそれで良かったのかと不安になります」との相談を受けると、「子どもはこうやって大人になっ
ていくのだなぁ」と思うとともに、私自身も「教師になったんだなぁ」と感慨深く思ったことを覚えています。
このように子どもは成長していきます。
目に見えて分かりやすい体の成長と同じく、心も成長していきます。
しかしながら、ある意味一方通行で成長していく身体に対して、心は行きつ戻りつしながら成長していくように感じています。
ある時は、妙に大人びた表情で「そういうこともあるよね。しかたないよね」と訳が分かったような表情をするかと思ったら、ある
時は「そんなことは許さない。何でそんな不公平があるのか」と激高する場面もあるのではないでしょうか。
そんな子どもたちですが、『自分の気持ちを分かって欲しい』と絶えず思っています。
そして、子どもたちは『自分の気持ちを分かってくれそうな大人』を絶えず求めています。
でも、実際には大人に心を許すというよりも、大人のアドバイスに対して疑い深い眼差しを向ける姿の方を多く感じますよね。
それは、『期待したのに、裏切られた』と、子どもが思う体験をしてきたからだと考えます。
今まで、長く多くの子どもたちと接してきて、感じているのは『子どもは純粋であり、理想主義者である』ということです。
『純粋・理想主義』という言葉は一見キラキラ輝いているようですが、実はその中に『間違いを許さない』という切れ味鋭い刃物を
持っていると考えます。
ですから、大人ならば信頼した人が、こちらの思い通りに考えたり、行動してくれたりしなくても、「まぁ、ちょっとがっかりした
けど、あの人にもしがらみとかあるから仕方ないかなぁ」と思えることも、子どもにはできません。
今まで、自分の思いに応えてくれた人が、ある時期待通りに動いてくれなかったとしたら、「なんだ。信じていたのに、あの人はあ
あいう人なんだ。信じて損をした。」となってしまうわけです。
そして、不幸なことに、そのようなことが重なると、「もう、大人なんて信じない。困っていても、話しても無駄だよね」となって
しまうわけです。
こうした経験から、「どうせ話しても、何ともならない」という経験則を抱いてしまうのではないかと考えます。
そんな子どもたちに対して、我々大人はどのように対していけばいいのでしょうか。
それは、根気よくきちんと接することと考えます。
私たち大人は、忙しさや面倒くささから、ついつい大切なことの説明を省略したり、端折ってしまったりするのではないでしょう
か。
大人同士ならば、何となく通じることでも子どもには通じません。(本当は大人に対してでも、同じことと思いますが‥)
そこで、「本当は○○すべきだったことを、どうして◇◇としたのか」と、丁寧に話すべきと思います。
それに対して、子どもが納得するか否かは子どもサイドの問題です。
心は言葉よりも遅いのです。
子どもに対して、そうした真摯な向き合い方を続けることによって、子どもの心の中に「この人ならば、信じて話してみよう」とい
う思いが生じると考えます。
こうした身近な問題をもとに、参加者全員で話し合ったり、ロールプレイでスキルの練習をしたりする会【コミュニケーションカフ
ェ】を開いています。
リアルでもOnlineでも開催しています。
詳しくは、このHPのトピックスをご覧ください。