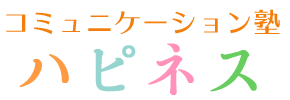子どもたちは、話したがっている ⑭ 事例②「先生、あなたの進路ではなく私の進路です」

いまどきの子どもたちの気持ちや考えていることについて、考えています。(詳細については以前のブログ参照)
スクールカウンセラーとして勤務していると、保護者や先生から「子どもたちが話さない」という相談をよく受けます。
そんな『話さない(と思われている)子どもたち』ですが、実は『自分の気持ちを分かって欲しい』と絶えず思っています。
そのため、子どもたちは『自分の気持ちを分かってくれそうな大人』を絶えず求めています。
では、我々大人はそんな彼等に対してどのように対していけばいいのでしょうか。
それは、ありふれた表現になってしまいますが、根気よくきちんと接することと考えます。
では、根気よくきちんと接するためには、どうすればよいのでしょうか?
その第一歩は、子どもの話をきちんと聴くこと(良い聴き手になる)ではないかと考えます。
しかし、実際に子どもたちに寄り添って話を聴いていると、(経験された方は分かると思いますが)いろいろ大変なこともありま
す。
(以下の詳細は、以前のブログを参照ください)
その1 「話をきちんと聴きたいけど、同じ話がエンドレスに続いて正直疲れる」
知っておきたい知識・スキル①
『本当の困りごとは、水戸黄門の印籠と同じく、終わり10分前に出てくる』
知っておきたい知識・スキル②
『【枠】をつくってあげる方が、話しやすいときもある』
その2 「話を聴いても、気の利いたアドバイスするって難しい‥」
知っておきたい知識・スキル①
『「気持ちをわかる」とは、「分かる」であって、「判る」「解る」ではない』
その3 「話し上手っているけど、聴き上手もいるの?」
知っておきたい知識・スキル①
『「聴き上手」のためには、波長合わせが大切』
知っておきたい知識・スキル②-1(この詳細は、前回のブログを参照ください)
『話を聴けないのは、相手を信じていないから?』
知っておきたい知識・スキル②-2
『話を聴けないのは、自分自身にOKと言えないから?』
第2部 具体的な事例をもとに考えてみます。
事例1 「うーん、訊き方下手!『大丈夫か?』では、誰も答えないよ」
知っておきたい知識・スキル①
『気になる話題を細かく具体的に尋ねることで、子どもが話す事柄が明確になり、話しやすくなる』
(ここからが、今回の内容です)
事例2 「先生、あなたの進路ではなく私の進路です」
先日、ある大学生が「大学受験のときに、大変だったのです」と、話してくれました。
「彼女は、本人曰く『なんちゃって進学校』(有名大学の合格実績を上げることに学校全体が熱心だけど、実はそんなに大したことはない)卒業ですが、2年生の3学期あたりから、先生たちに「どこが希望?」とよく尋ねられたそうです。「先生たちが、心配してくれるのは有難かったけど、もうちょっとほかっといて」という気持ちだったそうです。しかし、サークルなどでお世話になった先生がとても親身になってくれるので、「語学なんて勉強したいなぁ」と言った途端に、「家から通える方がいいのか」「私大か公立か」「語学を勉強して、どんなキャリアを目指すのか」等と、立て続けに質問されて、まだ何も具体的に考えていなかった彼女は、とても面喰ったそうです。
「今では、先生が自分のことを心配してくれたと有難く思うこともありますが、やはりそのペースに乗せられて、私を残して大学が決まってしまったという気持はあります。この大学、好きですけど‥」とのことでした。
さぁ、どんなことを感じられましたか?
教員だった身としては、この先生の気持ちも分かりますし、生徒思いの熱心な先生だなぁとも感じます。
きっと、先生方もこの学生に期待されていたのでしょう。
でも、でも‥なのです。
今、誰の進路を考えているのでしょうか?
この学生の進路ですよね。
しかし、こうやってみると、彼女の気持ちが置き去りにされて、どんどん話が先生方のペースで進んでしまっていっているように思
えないでしょうか。
もちろん、先生方は「○○さんのために」という意識で張り切られたのだと思いますが、一番大切な主体の心が「置き去り」にされ
てしまったように思えてなりません。
残念ですね。
もっとも、彼女自身が現在の大学に「満足」「納得」してくれているようなので、少し安心しましたが。
では、どうすればよかったのでしょうか。
ここで、「一方がもう一方に話す」という場面を想像してみると、次の二通りの場面があるかと考えます。
① 物事の説明をする ガイダンス
例えば、「進路希望表は水曜日までに提出してください。木曜日に、希望ごとに説明をします」というように、具体的な指示を与え
る場面です。言わば、業務連絡でしょうか。このときには、相手の気持ち云々というよりも、正確に伝えることが優先されます。
② 相手の気持ちに寄り添う カウンセリング
この場合は、「何かを伝える」ということではなく、相手の気持ちに寄り添うことが、優先されます。
みなさんは、友人に何か相談する時に、「私の悩みを相手に話したら、相手は魔法の杖でピピっと解決してくれる」なんて期待して
いませんよね。それよりも、「もう、今の私のこのイライラした気持ちを分かって」という気持ちから、話すのではないでしょう
か。
そう考えると、「○○すればいいんじゃない?」ではなく、「そうか、そう思っていたんだ。辛かったよね」という対応が必要では
ないでしょうか。
(とは言うものの、「相談さけても気の利いたアドバイスができなくて‥」と思う方は多いですが‥)
この大学生のケースでも、先生に尋ねられたときに、「うーん、まだ何も考えていないけど、せっかく先生が親切に尋ねてくれてい
るし‥強いて言えば語学かな‥」と、尋ねてくたれ先生の気持ちを忖度して言った一言が、勝手に一人歩きしてしまったわけですよ
ね。
そう考えると、「うーん、語学でしょうか」と彼女が言ったときに、「なるほど、語学に関心があるのね。それは、どんな時に思っ
たの」とか「そっか。語学いいね。将来海外で働くなんて考えたことあるの?」「語学に関心をもつようになったきっかけは何?」
といった類の質問を返して、「語学を中心にして考えてみようか。他にも、何か関心のあることがあったら話に来てね」と、今後に
相談を続けていくという形にしたら、どうでしょうか。
先生にしてみれば、「そんな悠長なこと」と言われるかもしれませんが、『進路決定の主体は誰なのか』をいつも忘れずに、彼女に
寄り添っていきたいし、そうするべきと考えます。
このように考えてみると、この場面で大切なことは「何かをすること(Doing)ではなく、寄り添ってあげる(Being)こと」ではないかと思います。
知っておきたい知識・スキル①
『相手の相談にのるときに大切なことは、DoingではなくBeing』
こうした身近な問題をもとに、参加者全員で話し合ったり、ロールプレイでスキルの練習をしたりする会【コミュニケーションカフ
ェ】を開いています。
リアルでもOnlineでも開催しています。
詳しくは、このHPのトピックスをご覧ください。